碧南で神を見た記録
2024/01/09
碧南市藤井達吉現代美術館が最後の持ち回り展示になる、「顕神の夢」展に{参加}してきました。
ありがたいことに、今回この企画をした三人、鎌田東二・京大名誉教授,江尻潔・足利美術館副館長、土方明司・岡本太郎美術館長、そして当館館長の木本文平先生の四人のトークショウを聴いたあと、記念の懇親会にて深く交流することができたので単に「見る」という経験を超えて「参加」することができました。
ですが、詳細を語る前にこの展覧会の持つ意味についてまだ見ていない方のために解説してみたいと思います。

この展覧会は四つのセクションに分かれているものの,それはあくまで便宜的なもので、全ては「神を感じる心」が「感じたものを見える形にする」という共通点で貫かれていることです。
そして
重要なことは一般にいわゆる「宗教画」が「宗教に属するもの」と解釈されているのに比して、この展覧会では「宗教に先立つもの」としての芸術の役割が位置付けられていることです。
それはこの展覧会が六会場で行われたものの、いずれも大本教の教祖の二人の「文字」で始められていることに象徴されます。
なかでも印象的なのはこの宗教の元祖である出口なおの「お筆先」です。文字の読み書きができなかったという出口なおは神がかることで筆を自動書記で行い、この大本教の教典が出来上がりました。
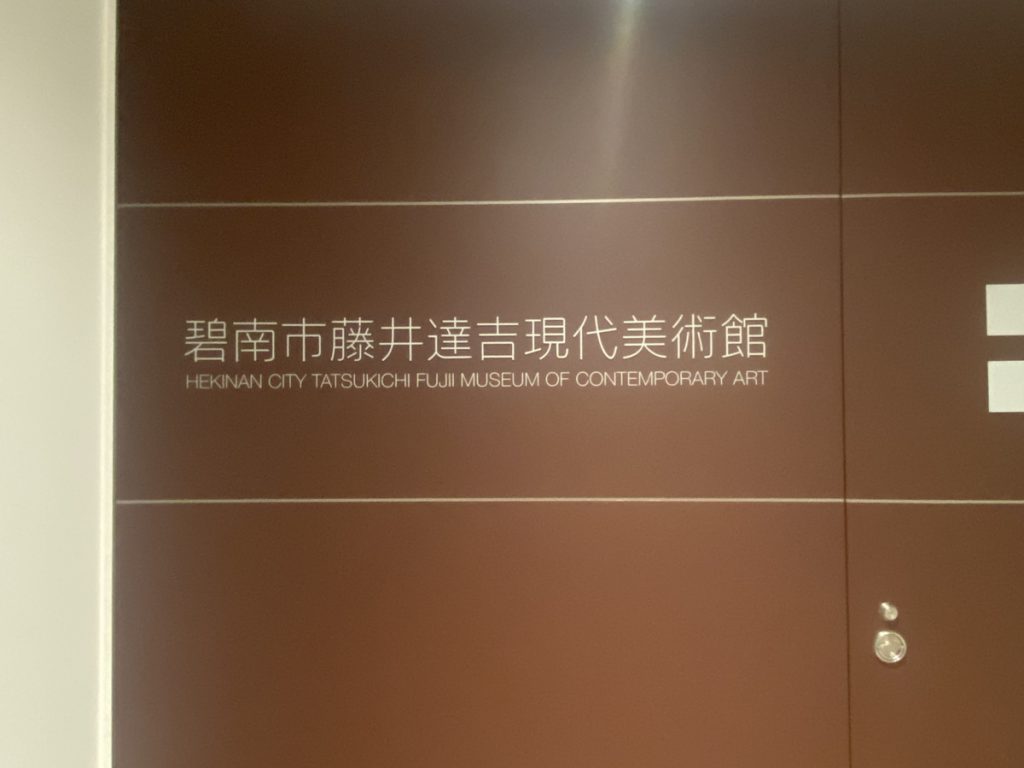
この展覧会で展示されているのはその一部、「うしとらのこんじん」です。書的にいうとこの文字は「と」が奇妙にぐるりと巻いており、どちらかといえば古筆の「か」のように見えますが、読み書きのできない人が書いたとすればむしろ言葉なき民の言葉として読み取るべきでしょう。ここに「地震」の神様が書かれていることは時節柄留意されることです。
ここにはもうひとつの自動書記で知られる「日月神示」を残した岡本神明の三貴人の絵が出ており、さらに現代の自動書記的作品も並べてあることでこの展覧会の主催者が文字による神示を主題として提示していることが知られます。
お察しの通り、この展示は特定の宗教を宣伝するためのものではなく、宗教者たちのここでの主題の提示のために彼らの作品は召喚されています。すなわち冒頭に書いたように、芸術こそが神を生み出す仕組みそのものであって、その逆ではない、というテーマです。

続いて私たちは中園孔二、村山槐多、関根正二、宮沢賢治の作品が続いて展示されるのを目にします。中園はまだ亡くなってまもない若い画家、村山槐多と関根はいずれも明治生まれの夭折の天才、そして宇宙と地上の理を詠う詩人、賢治。いずれもが若くして天啓を作品にした人たちです。
時代も立場も異なりますが、これらの作品の共通点に私たちは気付かされます。それは、これらの作品は網膜で見たものを描いたのではなく、心に映った絵を描いているという事です。
そして、神を直接感じられるアーティストという役割は、実は危険で、常人には達成し得ない立場だということも示唆されています。
その意味で、村山槐多の作品は重要です。性と祈りが一体となったような、神と人を結ぶかに見える村山槐多の作品は、本人の魂の容量を超えるかのような圧倒的な闇と光を放っています。
同じことは中園の絵にも言えるでしょう。幼稚性と神と悪魔が同時に降りてきたような作品は、おおいに私たちを高揚させ、同時に当惑させますが、本人の魂の感応性は長生きを許さず、本人の肉体自体が瀬戸内の海神に捧げされてしまいました。
明治から令和の時代に通じる二人の夭折の天才の物語がこの展覧会の霊性を高めているように感じられます。
この展覧会が特異な点はもうひとつあります。それはいわゆる物故の巨匠と現役の老若の作品が多数同じ主題でぶちこまれていることです。
選ばれた老若の作家が客観的にみてこの主題に最も適切であるかどうかはもしかしたら議論が分かれるかもしれません。たとえば物故作家であればここに熊谷守一や香月泰男を加える議論もあり得るでしょうし、現役アーティストでも同じテーマで招くべき人もいることでしょう。それでも彼らの創作にやはり共通していることはあります。それは彼らが理屈抜きに自らの直感に降りてきたものを表現しているということです。
彼らのそれぞれが神を引き合いに出しているかどうかは表面的なことです。大事のことは見えたもの見えるものだけに拘泥するではなく、事実上神あるいは自然や宇宙の「ことば」の依代{よりしろ}として彼らの仕事が働いていることです。
ここには草間彌生、OJUN、横尾忠則、真島直子、三宅一樹ら現代の老若の現役アーティスト、円空ら江戸の作品や、漁協に飾ってあった仏画、藤井達吉の聖画、など興味深いものが並べられています。
これを「抽象表現」とか「モダニズム」などで語られる戦後西欧美術の文脈と比較すると位相の「ちがい」が浮かび上がります。それは神を超える理性の美術(モダニズム)と神と共にいる美術(アニミズム)との「ちがい」です。
こんにちの現代美術マーケットにおいてはともすると技術とアイデアによる脱神化が試みられているようにも見えます。近頃のAIアートはまさに知性で神を否定しようとする、あるいは計算機で神を置換しようとする試みでしょう。
グラフィカルな美しさに席巻されている日本の現代美術の対極にこの展覧会の方向性は示されています。
さて、さらに付言しておきたいのが「文字」の問題です。芸術は言葉にならないものを表現する,とは俗によく言われることですが、しかし言葉は言葉にならないものを言葉にするためにもあるもので、例えば解読不能でも解読するべき言葉というものは存在します。読まれるのを待つ言葉。それはまさに「お筆先」であり「神示」です。不具者の言葉、無言の言葉、あるいは虫や鳥の言葉。
言葉の外にあるものを感じて編まれている言葉。
文字は依代として,なお有効で、特に漢字とかなを用いる日本語にはまだ汲み取りきれていない可能性が残されていると思います。
アートに書、というジャンルがありますが、「ジャンル」になった瞬間にこぼれ落ちてしまう「本当の言葉」はこの展覧会の見せた文脈にこそ存在するように思います。
ここに提示された言葉は「書道」とはあまり関係がない。しかしアートを依代とする生き方、生き方としてのアート、鑑賞者と製作者を深く繋ぐ「ことば」としてのアートを私たちはもう一度見直す時期が来ているのではないでしょうか。
この展覧会のトークショウは単にアートの論評ということをはるかに超えて、生きる私達の実相と「神」ないし「見えざるもの」とがどのように共鳴しうるか、という体験型の深い議論になりました。このショウの冒頭、鎌田先生が「ほら貝」と「角笛」を吹いたのですが、なぜか鼎談の最中、どこからともなくその笛の音が聞こえて来たのです。音響設備の問題だったのか、原因は定かではありませんか、会場にいた人間には、そこに神様がいるよ、というさりげない天意が示されたようにも感じられました。
そのあとの懇親会でよかったことは、何より、現役の画家が多数参加したことです。物故は物故、現役は現役、ときれいに分けられている展示では、このたびのように芸術への一体感、そして祝祭感は生まれようがありません。芸術が生きて感じられるのは、死したものの芸術と生きているものの芸術が敬意という接着剤を通して交流する瞬間にあります。そうした刹那を共有できたことは幸福なことでした。

展覧会はこの会場で最後。
https://www.city.hekinan.lg.jp/museum/event_guide/kikakuten/20106.html
| 展覧会名 |
碧南市制75周年記念事業 開館15周年記念 顕神の夢 ―幻視の表現者― 村山槐多、関根正二から現代まで |
| 会期 |
2024年1月5日(金曜日)~2月25日(日曜日) ※会期中、展示替を行います。 前期:1月5日(金曜日)~1月28日(日曜日) 後期:1月30日(火曜日)~2月25日(日曜日) |
- PREV
- 原宿でカプーア。水面下の現実の露出。
- NEXT
- 本を出しました。
